建築の確認審査の仕事の慣習をまとめました。
確認審査は、確認済証や検査済証の発行、他には構造計算適合判定、省エネ適合判定、住宅性能評価等を行います。
確認審査は主に裁量権を持つ行政が行っていた仕事です。
例えば退職した人の仕事を引き継ぐと一気に仕事量が増えたり、対応の大変さも多々あります。
民間が審査業務の大半を取り扱うようになり、設計、施工、監査とどのような関わりとなっているのかその慣習をまとめていきます。
- 設計担当、特に意匠担当との関わりは面倒では?
- 職種を少しずらすとどんな違いがあるのか。
- 行政系の仕事の残業は?
- 監査による仕事の増加の仕組み
参考にご覧ください。動画では仕事の日常をご覧ください。
確認審査~法規・ルールを扱う仕事
専門性・余暇時間
日常を通して建築関連の法律を扱うため、法律に詳しくなります。
製作からみの職種とは距離を置くため、能動的な人との調整は少ない部類に入ります。
人に伺い立てることは少なく済む方だと思います。
多数の案件を短期的ターンで扱うため、仕事の経験スピードは高い方だと思います。
但し即業務対応を進めやすいこと等もあり転職者の方が多めです。
在宅ワークも取り入れられており働き方の自由度があります。
個人のスキルで業務の効率化の工夫の余地があります。
なお仕事で利用する法令集としてこちらが活用されています。
電話の慣習
審査に後戻り、設計からの質問などが上がると、時間のロスとともに対応のミスも誘発します。
一部の設計担当・現場担当・発注者。威圧的な同僚(例えば審査機関には新卒からゼネコン出身者~設計事務所出身者まで集まります)からは催促、クレームがきます。
(言われたことがない、まだ消防に送っていないのか、なぜすぐ返信しないなど)
※消防送付(確認済証発行手続きの最終段階)
確認依頼などメールで済む内容を何度も電話する設計担当者もおり、他の案件審査、業務に支障や負荷が蓄積します。
長々と話し勝手に切るなど業務を妨げるレベルもあります。
解釈の難しい質問(運用に伴うものなど)を設計担当からあげてくることがあるため慎重な対応も必要となります。
議事を取るため質問を長く続けられることがあります。
一方で工事範囲後など審査対象外の内容を質疑されることもあります。
本受け図書を受領後の消防送付前も修正が頻発する。
決済確認等を行う結果、一度確認済の図面が修正前に戻っている、添付漏れも頻発します。
設計のeasyミスにも関わらず消防へ送付済の催促、設計者のやるべき図書の差し替えを依頼する設計担当者も頻発します。
申請の添付図書がないなか、設計から発する言葉
「添付、差し替えないとけないのか。」
「一刻を争う」など。
「ここに全図書アップしないとダメなんですか。」過剰な人物は、言葉尻を掴み続ける。
※本受け(確認済証発行手続きの最終段階)
【取引相手となる設計の一幕】
検査
施工者等立ち会いの検査では、大手施工会社でも排煙検査に殺虫剤を使用するなど、信用がゼロになるようなことが行われます。
監査を気にしながら仕事を進めてきた文化。
設計・施工と同じく、審査機関も公共機関等第三者の監査を受けます。
約款等で監査結果を委員会等に報告する場が設けられ、最終的に指定を受けた行政へ報告するためです。
適切な監査内容を報告しないと、報告の場で昔ながら即、問い詰めから入る委員もいます。
←適切な報告だけしないといけないという圧力を受けます。
監査者からは「不足していた」と誘導されることもあります。
結果、沢山の根拠を揃えるため、審査から設計の各層まで仕事が増えるきっかけになります。
監査結果を受け、書類不足をチェックする項目が増えるだけで、消防送付、決裁前の手間が増加します。
監査は行政出身者が担当することもあり根拠・白黒をはっきりつけさせてくる傾向があります。
監査、会議が減ることへの期待は少ないですが、審査項目が増え、設計担当等からクレームを受けることは避けたいことです。
(基準が明らかでない内容も仕事現場では出くわします。ただあくまで根拠が揃うと問題にはならないはずですし見解の集め方にも工夫の余地はあります)
案件数過大
設計担当が抱える数を上回り日常の仕事時間に一人で詳しく調べるような時間はとりにくい。(メンバーの協力で補われることもあります)
人員が減っても仕事量に対して増員することは圧倒的に少ない。
まとめ
法律に詳しくなり、短期的に仕事の経験値を高めたい、能動的にできる仕事をしたい、残業を少なくしたい。
という方には、まだまだ現実的に相応しいと思います。
また要領を掴むと希望も持てそうです。。
審査業務には知識を活用しての仕事が多いため、資格の取得が大切です。【知識として役に立ちます】
【スクールを利用することで何事も早めに成果ができます】
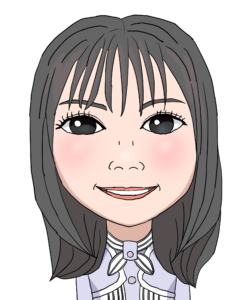
【☟ 転職先を探す】
組織的にDX化の期待値が向上することを見越せます。
設計も業務の一環で実務経験により知識は後から身につくため、適応次第で仕事は対応できるようになります。
この記事で触れたよう慣習はDX化の進展に伴い、働きやさくなっていくはずです。
こちらから求人を見つけられます。
【動画の参考書籍】

マネジャーのための人事評価で最高のチームをつくる方法 「査定する場」から「共に成長する場」へ



